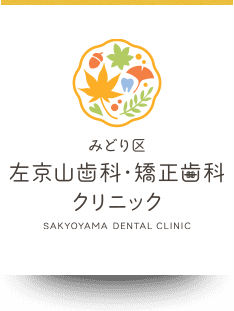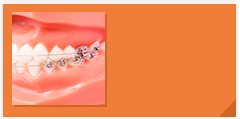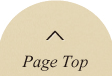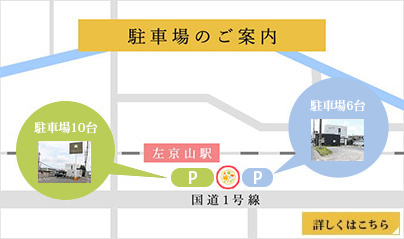子どもの歯ぎしりが心配という親御さんへ:原因と対策を解説

こんにちは、左京山歯科・矯正歯科クリニックの院長の宮崎です
子どもが寝ているときに「ギリギリ」と歯ぎしりをしていると、親としては「歯に悪影響はないか」「ストレスが原因ではないか」と心配になりますよね。実は、子どもの歯ぎしりは珍しいことではなく、成長過程の一環として自然に起こることもあります。しかし、頻繁に続く場合や、歯や顎に負担がかかっているように見える場合は、適切な対策が必要です。本記事では、子どもの歯ぎしりの原因や影響、対策について詳しく解説します。
子どもの歯ぎしりの主な原因
-
歯の生え変わり
子どもの歯ぎしりの最も一般的な原因は、歯の生え変わりです。乳歯から永久歯に移行する際、噛み合わせが不安定になり、無意識に歯をこすり合わせることで調整しようとします。これは一時的なものであり、成長とともに自然に収まることが多いです。 -
顎の成長や発達
子どもの顎は成長段階にあり、上下の歯の噛み合わせが変化することがあります。この適応のために歯ぎしりをすることがあり、特に寝ている間に無意識に行われることが多いです。 -
ストレスや精神的な要因
大人と同様に、子どももストレスや緊張を感じると歯ぎしりをすることがあります。環境の変化(引っ越しや幼稚園・学校の変化など)、不安や興奮などが影響することがあります。 -
噛み合わせの異常
噛み合わせに問題があると、歯ぎしりをして調整しようとすることがあります。例えば、上下の歯がうまくかみ合わない場合、無意識に歯を動かしてしまうことがあります。 -
鼻づまりや口呼吸
鼻づまりがあると、口で呼吸する習慣がつきやすく、それに伴って歯ぎしりが起こることがあります。これは口の筋肉の緊張を引き起こし、顎の動きにも影響を与えるためです。
子どもの歯ぎしりによる影響
多くの場合、子どもの歯ぎしりは一時的なもので、大きな問題にはなりません。しかし、以下のような症状が見られる場合は注意が必要です。
・歯のすり減りが激しい
乳歯や永久歯が大きく削れてしまうと、知覚過敏や虫歯のリスクが高まることがあります。
・顎の痛みや違和感
強い歯ぎしりが続くと、顎関節に負担がかかり、顎の痛みや開閉時の違和感を引き起こすことがあります。
・睡眠の質の低下
歯ぎしりが強すぎると、睡眠の質が悪くなり、日中の集中力低下や疲れやすさにつながることがあります。
子どもの歯ぎしりへの対策
-
ストレスを減らす
子どもが安心できる環境を作ることが大切です。リラックスできる時間を作ったり、寝る前に絵本を読んだりすることで、ストレスを軽減できます。また、親子のスキンシップを増やすことも効果的です。 -
噛み応えのある食べ物を取り入れる
硬い食べ物をよく噛むことで、顎の発達を促し、噛み合わせが安定しやすくなります。例えば、根菜類(にんじん、大根)、ナッツ類(アレルギーに注意)、フランスパンなどを適度に取り入れるとよいでしょう。 -
正しい睡眠環境を整える
寝る前のテレビやスマホの使用を控え、リラックスした状態で眠れるようにしましょう。暗めの照明や静かな音楽を活用するのもおすすめです。 -
歯科医に相談する
歯ぎしりが長期間続いたり、歯が削れているのが気になる場合は、歯科医に相談しましょう。必要に応じて、マウスピースの使用を勧められることもあります。
まとめ
子どもの歯ぎしりは成長の一部として自然に起こることが多く、特に歯の生え変わりや顎の発達に伴うものは心配いりません。ただし、歯が極端に削れる、顎が痛む、睡眠に影響が出るなどの症状がある場合は、専門家に相談することが大切です。日常生活の中でストレスを減らし、噛む力を鍛えることで、歯ぎしりの頻度を減らすことも可能です。親御さんとしては過度に心配せず、子どもの成長を見守りながら適切に対応していきましょう。